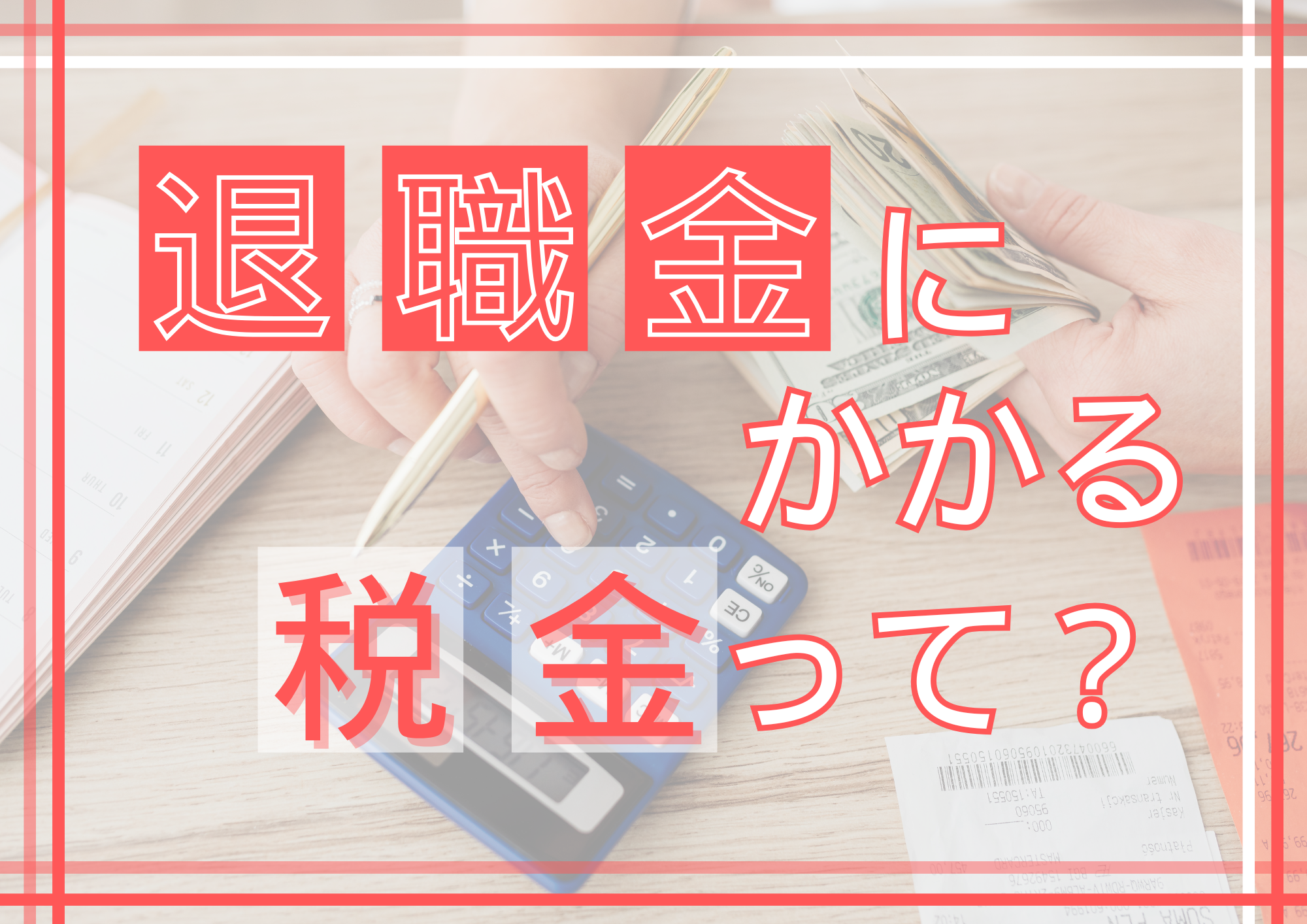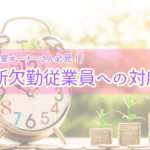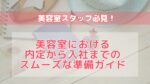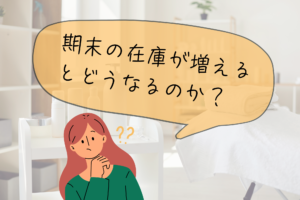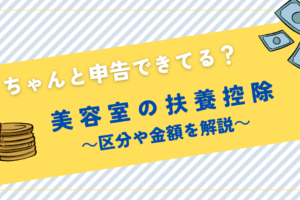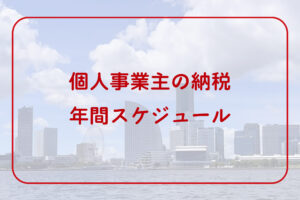退職所得課税制度については、2023年6月に政府が今後見直しを行う方針であることが明らかになり、報道などで目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
従来の美容室では退職金制度がないことも多く、気にされることもあまりなかった話題ですが、実はオーナーが加入できる小規模企業共済や、従業員の方も含めて最近加入されている方が増えているiDeCoなどにも関わってきます。
どう関わるのか、という話の前に、まずは現状の「退職所得課税制度」について確認しておきましょう。
注:本記事は2024年1月現在の税制によるものです。
目次
- 退職所得と給与所得
- 退職所得になるもの
- 退職所得にはどんな税金がかかるのか
- 退職所得にかかる税金の計算
1.退職所得と給与所得
毎月、勤務先から受け取る給与や、お店によっては年に何回か支給される賞与。
お店をやめるときに支給される退職金。
どちらも「働いたことに対して勤務先から受け取るもの」という点は同じです。けれども従来の退職金は、長年勤務して引退するときに老後の資金としてもらうもの、という意味合いが強く、そこにたくさんの税金がかかると困るという配慮で、給与とは異なる税金のかけ方をしましょう、というのが現状の退職所得課税制度です。
税金を計算する際は、退職金は退職所得、と給与や賞与は給与所得というように、そもそもカテゴリがわかれています。給与所得は「総合課税」と言って、ほかに所得があると合算したうえで税金がかかりますが、退職所得の場合は、退職所得だけでわけて計算します。さらに、退職所得にかかる税金計算は「退職所得控除」を差し引くことができるので、金額が大きくなっても比較的、税金の負担は低くなります。
2.退職所得になるもの
では「退職所得」カテゴリに入るものは、どのようなものがあるのでしょうか。
一番わかりやすいのは、定年退職で勤務先から一時金として受け取る退職金でしょう。
なお、全額を一括で受け取る(一時金)と退職所得になりますが、年金のように何年かにわけて受け取ると雑所得になります。
勤務先以外からの受取りで退職所得に該当するものには、たとえば小規模企業共済の共済金やiDeCoの老齢給付金があります(いずれも一時金で受け取った場合)。
また少々毛色が異なりますが、解雇予告手当も退職所得として取り扱われます。
3.退職所得にはどんな税金がかかるのか
退職所得に係る税金は所得税(復興特別所得税を含みます)と住民税です。
かかる税金の種類に関しては、給与や賞与と同じです。ただし、計算方法が異なります。
ちなみに、社会保険料はいわゆる退職金にはかかりません。
4.退職所得にかかる税金の計算
所得税や住民税がかかるのは給与や賞与と同じでも、計算方法は大きく異なります。
退職所得にかかる税金の計算は次のような手順で行います。
(1) 勤続年数から「退職所得控除額」を計算する
(2) 退職金等の額から退職所得控除額を差し引いて「退職所得の金額」を計算する
(3) 「課税される退職所得の金額」に税率をかけて控除額を差し引く
それぞれの計算を詳しく見ていきましょう。
(ここでは原則的な計算方法のみ、ご紹介します)
(1) 勤続年数から「退職所得控除額」を計算する
「退職所得控除額」というのは勤続年数に応じて退職金から差し引くことができる金額です。計算式があるので、それに当てはめて計算します。
【退職所得控除額の計算式】
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数の期間に1年に満たない期間がある場合は、1年に切り上げて計算します。
退職所得控除額が80万円に満たない場合は、80万円として計算します。
(2) 退職金等の額から退職所得控除額を差し引いて「退職所得の金額」を計算する
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額
なお、勤続年数が5年以下の役員の場合、上記計算式の「× 1/2」が適用されません。
また、役員以外でも勤続年数が5年以下の場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の「× 1/2」が適用されません。
(3) 「課税される退職所得の金額」に税率をかけて控除額を差し引く
①所得税の計算
以下の計算式で計算します。
課税される退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)×税率×控除額
税率と控除額は速算表を参照します。
国税庁タックスアンサー「別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
退職金等の支給を受ける際に、勤務先等に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、上記のとおり計算して源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません。一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、確定申告を行うことにより所得税等の精算を行います。
②住民税の計算
個人住民税には市町村民税と道府県民税があります。市町村民税の税率は6%、道府県民税は4%です。それぞれの税率にもとづいて計算します。
課税される退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)×税率
まとめ
働き方が変わってきたことで、ひとくちに退職金と言っても従来の退職所得課税制度にそぐわない部分も出てきており、今後、制度が見直されることと思われます。
どう変わるのかを理解するためにも、まずは現状の制度をおさらいしてみてください。
出典
「内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2023」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2023/decision0616.html
国税庁タックスアンサー
「退職所得となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm