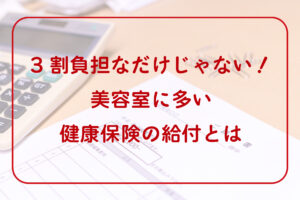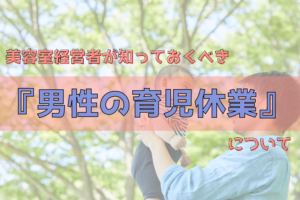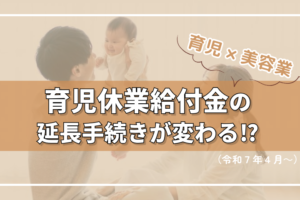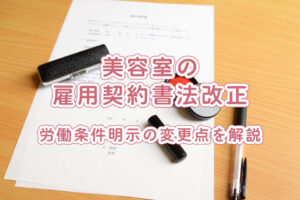今年、令和7年4月より、育児に係る重要な法改正があります。
今までの働き方から変更が必要になったり、スタッフに説明が必要になったり・・・
と、労務問題に直結することになりますので、オーナー様は必見です。
| 目次 |
1.改正の趣旨
今回の改正のねらいは、男性も女性も仕事と育児・(介護)を両立できるようにするために、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充などがあります。
様々な働き方ができるようになることで、育児と仕事の両立を後押しするという目的です。
2.具体的な改正ポイント
下記、変更箇所を赤字(太文字)で記載しております。
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち、事業主が2つを選択
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。
③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し、事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
3.必要なこと
令和7年(2025年)4月1日より施工開始となりますので、それまでに就業規則の見直し、改訂が必要となります。
また、10月1日から「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等」、「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が施行されますので、そちらもあわせて就業規則へ反映をする必要があります。
措置に対する個別の周知・意向確認を行う必要もでてきます。
4.よくある質問
Q:「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)」については、無給でもよいでしょうか。
A:「養育両立支援休暇」を取得している期間については、労働者は労務を提供しないため、無給でも問題ありませんが、企業独自に法を上回る措置として有給とすることは差し支えありません。
Q:「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別の周知・意向確認について、事業主は、いつ、どのような内容で、どのような方法により実施すればよいですか。
A:3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、労働者の希望に応じてフルタイムで働くことができるよう、職場のニーズを把握した上で、「柔軟な働き方を実現するための措置」を2つ以上講じ、労働者が選択できるようにしなければなりません。
その措置については、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間〈1歳11か月に達する日の翌々日から起算して1年間(2歳11か月に達する日の翌日まで)〉に、
- 「柔軟な働き方を実現するための措置」の内容
- 「柔軟な働き方を実現するための措置」の内容の申出先
- 所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度及び深夜業の制限に関する制度
について、当該労働者に対して個別に周知するとともに意向確認を行う必要があります。
また、個別の周知及び意向確認の方法は、
- 面談
- 書面の交付
- FAXの送信
- 電子メール等の送信 のいずれかによって行う必要があります。
※③、④は労働者が希望した場合のみ実施可
※①については、オンラインによる面談可
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に実施されていれば、定期的に行っている人事面談等とあわせて実施いただくことも可能です。
なお、個別周知と意向確認は、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出が円滑に行われるようにすることが目的です。
そのため、取得の申出をしないように抑制する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことをことさらに強調するなど、取得や利用を控えさせるようなことは行ってはなりません。
5.まとめ
法改正によってこれまでと働き方が大きく変わる会社も出てきます。
社会の流れをよく見ながら、スタッフにとっても会社にとっても、良い働き方が築けるようにしていきたいですね。